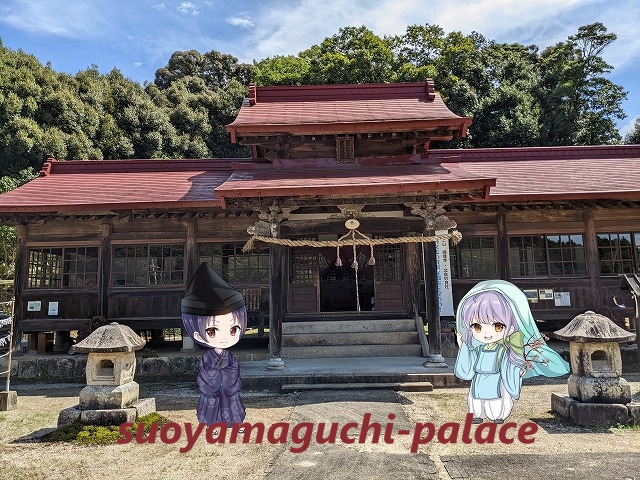多々良茂村 妙見社を氷上山に勧請し氏寺と一所に

多々良茂村とは?
大内氏第十一代当主とされている人物です。あくまで伝承の域を出ない時代の方なので、実在したのか否かについては不明です。
下松の妙見社を氷上山に勧請したのは茂村であるとされており、系図、古文書、研究者の本そのた諸々において、その一点だけで必ず名前が挙げられています。それゆえに、大内氏の氏寺や氏神などを研究している方ならば、必ずその名前をご存じですが、それ以外のことはすべて謎です。
そもそも、茂村が勧請したという点も「伝承」ですので、真相はわかりません。
多々良茂村の基本データ
大内氏第十一代当主
生没年 不詳
下松にあった妙見社を氷上山に勧請した
(典拠:『大内文化研究要覧』)
大内氏の暗黒時代に「事蹟」が残る数少ない当主のひとり
文字史料がない(もしくは史料が乏しい)ため、何もわからない時代を歴史上の「暗黒時代」とすれば、大内氏のそれは、史料に初めて名前が現われた十六代・盛房以前のすべての当主が「暗黒時代」の人々。その意味ではこの人、茂村も紛れもなくそのひとり。
史料は何もないのに、系図には名前が載っている。そのことを以て、「実在していた」とすることは、歴史学上許されぬようなので、その意味では始祖・琳聖を含めて全員が、詳細不明な謎の存在である。
ならば、系図に書いてある「だけ」のことは信じてはならないのか? この点が常に納得がいかない。系図というものは、後から手を加えたり、都合の悪い部分は敢えて伏せたりと、意図的にでっち上げることができるものであるらしい。そのような「でっち上げ」が行なわれた痕跡は、最新の研究によって曝かれてしまったりするので、確かに信用ならない部分はある。
始祖が日本にやって来たのが、聖徳太子の時代であったとしたならば、とりあえず文字記録は残せた時代。始祖については、後世の歴代当主たちが自らのルーツを輝かしいものにするために、多少手を加えたとして、それ以後の人たちはどうなんだろうか。何の事蹟も書かれていないような名前しか出て来ない人については、むしろ普通に信用していいような気がする。始祖以降「六代欠落」しているのに、そこに強引に適当な名前を当てはめて埋め合わせをするような工作はされていない(後世の無関係な人々が行なった悪戯は除く)。⇒ 関連記事:「六代欠落の問題について」
世代数が合わないという理由で適当に名前を考えて埋めておくようなでっち上げをしたのだとしたら、「欠落」はないはず。そんなことから、名前だけの人も含めて、それなり信じていいのではなかろうか、と思う(個人的見解です)。
妙見社を氷上山に勧請
多々良茂村は、十一代当主であるという系図上の流れと、妙見社を氷上山に勧請したという二点だけが確認できる当主。しかし、大内氏といったら氷上山だったり、妙見信仰だったりが最大の魅力の一つでもある一族なので、この人の名前は「暗黒時代」の中では突出して有名なのではなかろうか。
妙見社を氷上山に勧請したことにより、氏寺と氏神がひとつところにまとまり、一族が様々な祭祀を執り行うにも便利となった。確かにひとつにまとめられて便利になったことはわかるが、これって、十一代に至るまで気付かなかったんですか? と考えると、それまでの当主たちが、二つを分れた場所に置いていたことのほうが疑問に思える。暇すぎて氷上山から鷲頭山まで移動することを面倒と思わなかったのか、単に「ひとつにする」という発想がなかったのか。
かくいう執筆者も今でこそ三十一代まで見なくても書けるが(大友から来た傀儡は数えない)、それ以前は何となくしか分からなかった。それでも、茂村だけは相当早い時期から覚えていた。そんなわけなので、実はとてつもなくメジャーなお方なのではないかとすら思える。
だって、まずは氏寺・氏神の話と、異国から来た始祖に魅了される人が多いこの一族で、氏寺・氏神の歴史をチラ見すると「茂村が勧請し」と書いてあるところに目が行くので。それこそ、「史料がないので」本当かどうかすらも分からないのに。いや、茂村が妙見社を勧請したことの真偽のみならず、実在したかどうかすらも不明なわけです。にもかかわらず皆、茂村が実在しなかったなどあり得ないかのように、「妙見社を勧請した人です」と書いている。妙見社が下松から勧請されてきたらしいことは既成事実なので、誰だか分からない先祖によっていつだか分からない時期に云々とするより、ちゃんと名前があったほうが聞こえがいい。研究者に睨まれたくなければ「伝」をつければいいだけ。とはいえ、この問題、もう少し考えてみたほうがいいような気もしている。

氏寺の創建と氏神の勧請年代を考える
そもそも、二つところにあった氏寺と氏神を一つにしたと言っても、それぞれがいつ誰によって創建されたのかも不明。氏寺の創建者と年代は知られているし、氏神(社)についてもだいたいのことはわかる。けれどもいずれも「伝承」。氏寺は、存在を否定までされている始祖の創建ということなので、創建年代についても信じていいものか、甚だ疑問。妙見社の創建については、降松神社のご由緒からわかる。ただし、いっとうはじめは北辰降臨からということだから、それが隕石襲来であったとしても、何年のことかなど誰にもわからないのでは? というのが本音。始祖来朝時点で社は存在していなければ伝説と合致しないので、始祖がインチキなら来朝した年代などわかろうはずもない。
インチキかどうかはおいておくとして、長い長い時間をかけて、先祖伝説を編纂してきた一族のこと。妙見社が、十一代・茂村の時に勧請されたことになっているのにも、きっと何らかの意味があるのに違いないと感じてしまう。ただし、どういう事情があったのかについては、それこそ史料がないために不明である。やはり残念。⇒ 関連記事:大内氏先祖伝説制作秘話
「史料がない」ことはわからない、と言われたらそれこそ何もわからなくなる。氏寺と氏神社の創建年代が、不確かな伝承でしかないとしても、それらをひとつにまとめた年代がわかれば、少なくともその時点で両者が存在していた証拠にはなる。ありもしないものをひとつにまとめることはできない。そして、茂村が妙見社を勧請した年代については記録がある。ただし、悲しい哉、これまた神社の記録でしかないので、寺社の縁起や由緒は信用できないとする学術的な面々には証拠不十分となる。そういう方々にはお引き取り願って、氏寺、氏神社の創建、氏神勧請の年代についてまとめてみると、以下の通り。
- 推古天皇十一年(611) 琳聖来朝 ⇒ この数年前に「北辰降臨」があって、人々がその神託をきいて社を建てたのが妙見社の前身なので、社の創建年代はこの年を下らないはずという意味で採用した年代
- 同二十一年(613) 琳聖、興隆寺創建
- 天長四年(827) 茂村、下松から氷上山に妙見社を勧請
(年代典拠:『大内文化研究要覧』「大内氏関連総合年表」6ページ~)
この、茂村代に下松から妙見社が勧請されたという「通説」は、じつは、大内氏の「自己申告」による。いわゆる『大内多々良譜牒』(氷上山興隆寺の縁起でもある)に、そのように書かれているのである。つまりは、琳聖がらみの多くの伝承同様、最終的にこの「説」を提出したのは、大内氏自身である。むろん、寺社縁起などの学者が史料として数えない伝承は、あったとしても完全に無視している(個人的に、そういうやり方は好きではないのだが)。

氷上山興隆寺縁起 (大内多々良氏譜牒ともいう) に、――中略――大内茂村がこれを大内県の氷上山に勧請し、氷上山の神祠、仏閣、僧舎等の結構は鷲頭山に十倍していたと記している。この氷上山妙見社上宮、下宮が勧請された時代を、大内茂村の時とするも、何年であったかは記していない。ところが、この妙見社の由来についても、異説がある(以下省略)
出典:『大内村誌』河野通毅
『譜牒』にも記されていない妙見社勧請の年代が、どこから降って湧いたのかと言えば、『金藤家古記』なる文書が典拠であるらしい。そして、この金藤家というのは、「下松妙見社の旧神主の家」の方々という(参照:『大内文化研究要覧』)。同様のことは、『大内村誌』にも詳しく記されている。ただし、いずれの研究書も、この「年代」が正確であるかどうかについては、疑問を投げかけている。『大内村誌』に至っては、「未だ推測の域を出ない」としながらも、「寧ろ興隆寺も琳聖太子創建というより大内茂村の勧請になるものとする方が、より真実性があるのではあるまいかとさえ思われる」と書いている。興隆寺が「勧請された」としたら、どこからなのか? いうまでもなく、下松だろう。
ひとまず年代を正しいと仮定すると、氏寺と氏神離れ離れの場所にあった期間は約二百年もの長きにおよぶことがわかる。ずいぶんと長いこと、寺と社の祭祀のために、山口―下松間を行き来していた勘定となり、移動だけでもたいへんだったことだろう。ここへきてやっと、ひとつところにあったほうが楽である、ということに気付いた茂村という人はなかなかの切れ者だ。
何となくだが、そもそも「北辰降臨」の地が下松、氏神もそこにあったのならば、最初に住んでいたのは社のあったところで、大内には後から引っ越したのではないかと思っているのだが、その思いはさらに強くなった。同じようなお考えの研究者の先生もおいでだが、古すぎて証明は不可能なのか、これといった「絶対説」は見たことがなく、普通に山口に遷して当然でしょうという「通説」が幅をきかせているように見える。
氏寺・氏神一所の繁栄
茂村による妙見社の勧請が、氏寺と氏神をひとつところにまとめたことで、大内氏の氏寺・氏神信仰を揺るぎないものとし、その祭祀もさらに盛大なものとなったと語られることが多い。まあ、これは、事実に基づいていると考えて差し支えないだろう。しかし、それらは大内氏が西国一の大大名にまで発展していく中で、次第に整えられていった過程があったはず。茂村による勧請と同時に盛大化したわけではないだろう。ここは、単に「スタート地点」にすぎない。
『大内村誌』が、あるいは氏寺すらも、茂村の勧請前は下松にあったのでは? と書いているくらいだ。さすがにそこまでは言い過ぎかもしれないが、強ちデタラメとも思えないのは、勧請年代が正しいと仮定した場合、数百年にもわたり、祭祀は二箇所に分れて執り行われていたこととなり、規模も小さくどうでもよかったか、あるいは、最初は山口とは「別の場所」に存在していたものの、両者は一箇所にあったゆえ、祭祀については特に面倒ではなかったと考えても許されるだろう。
茂村勧請という「事実」は『大内多々良譜牒』から来ている。興隆寺の氏寺・氏神一所の祭祀が最高潮に達した時代に書かれた史料が典拠になっているのである。要は後から論を勧請当初の時代に当てはめてはいけないのであって、恐らく、このくらいの時代に勧請された、という程度が関の山かと。むろん、先に氏寺在りきで、それが始祖の代創建ならば、十三代までにはかなり整備が進んでいたとも考えられ、そこに氏神を迎え入れたのなら、そこそこの規模になっていた可能性はある。でも、証拠はない。
夢多き乙女が「素敵」と想像することと、学術研究はイコールになってはならない。しつこく言っているように、乙女かどうかは別として、ここは学術研究を目的とする場ではないので、想像は自由。ただし、研究者の先生のお立場でそれをやることは、かなり危険なことになりかねない。
『大内氏史研究』においては、もはや、大内氏礼賛のあまり、研究書とは思えないような記述になっしまっている。
十一代茂村に至って、この神霊(妙見社に祀られた神のこと)を大内氏の本拠大内県の氷上に勧請して氏神と定め氏寺興隆寺と一所にした。
鷲頭妙見宮を氷上に勧請せるは、茂村に至って多々良の家運が、ますます隆盛となるに随って、その氏神の祭祀もまた、盛大に執行されることとなって、氏神と氏寺とが別所に在っては、不便であるから、多々良の根拠地に在る氏寺と一山に鎮祭したのであることを語るものである。
大内氏由来崇神奉仏の念深く、始祖琳聖は氷上に興隆寺を草創したと伝えられ、後に天台宗となって、大内氏氏寺となり、十一代茂村は琳聖来朝に由緒の深い鷲頭妙見社を氷上山に勧請し、上下両宮を建てて氏神と崇めたことは、余りに顕著なる事実である。
出典:『大内氏史研究』御薗生翁甫
それぞれ、3ページ、3ページ、287~288ページから引用。マーカー執筆者
ここには、茂村が実在したかどうかを疑問視する思想も、下松こそがルーツという思想も全く見られず、既成事実として「茂村が勧請し、信心深い大内氏の氏神・氏寺として大いに発展した。根拠地・大内の地で」と書いてあるだけである。
さて、では、『大内実録』では、このことをどう記しているか。
(前略)宗範、茂村を生む。鷲頭山より妙見を氷上山に勧請す。
出典:『大内氏実録』近藤清石、16ページ
この一文は『大内譜牒』から採取したことになっているから、『大内村誌』同様、典拠はやはり、大内氏の「自己申告」である。『大内氏史研究』も出典は同じと思われるが、「氏寺氏神一所に」とか「多々良氏の家運がますます盛んとなって祭祀も盛大になった」とかいうのは、先生の推測であって、どこかに史料があるわけではないことがわかる。無論、偉い先生の推測であり、普通に考えてもなるほどと思い至る程度のことなので、大内愛深い方としては当然の帰結といえる。ただし、「あまりに顕著なる事実である」というのはいかがなものか。偉い先生のお言葉なので、どなたも否定しないが、そこらの素人が言ったら日本史の教授辺りから落雷必至であろう。
大内が中心となったのはいつから?
大内氏の先祖たちについて、正確なことはわからないものの、朝鮮半島から来た人々が周防国に土着した。そして、その根幹地は「大内」だった。それゆえに、やがてそれが「名字の地」となり、「大内氏」として教科書などに載るような存在となった。本来は多々良氏なのだが、それは源氏にも足利や武田や佐々木があるのと同じ。これらの有名な方々はともかく、通史類にちょこっと登場するだけの方々について尋ねられて、即源氏と答えられるのは彼らとゆかりのある地にお住まいの地元の方々か、研究者だけ。無名になればなるほど、分家前の ○○氏は一般人には知られていない。それに、知らなくても全く問題ない。生きていける。
問題は彼らはいつから大内の地に住み着き、やがてそれが名乗りになるほど、以後もずーっと彼の地が心の古里になったのか、ということ。「伝承」によれば、始祖が来朝し、聖徳太子と面会して「大内県」を賜り、それを「采邑」としたと。聖徳太子との面会を終えた後、下賜された地・大内に下向しそこに定住した云々と。これまた、琳聖が実在の人物ではないとされると、およそ信用できない話となる。ただし、現在は、聖徳太子すら実在しない人物だったとする説があるくらいなので、実在しない人物に面会することは不可能だから、もはや何を信じてよいのかわからなくなる。聖徳太子が実在した否かの問題については、現在のところまだ完全に否定されるには至っていない模様であり、厩戸皇子なる聞き慣れぬ人物名が書き加えられた以外、参考書からも消えてはいない。
琳聖なのか、ほかの何者かなのかわからないが、始祖にあたる人物が来朝し大内の地に住み着いたのがいつ頃のことなのか、あまりに当たり前すぎるゆえにか、どなたも正確なところを記してくださってはいない。伝承を信じて、推古天皇の時代からそこにいるのだと信じている方々がおられるだけである。
学者たちが認めている「史料に出た最初」が平安末期。その時点で、国衙の役人中、それなり力を持つ一族であったらしきことが知れている。その辺以降、どの辺りに所有地があって……ということも記録が出てくるが、その中に当然「大内」の地も入っている。
それ以前のことは、史料的には不明。ところが、妙見社を大内の地に勧請したのは茂村。それ以来氏寺・氏神ひとつになってさらに繁栄したという点は何やら既成事実化している。この際、素直に信じておこう。だとするならば、茂村が妙見社を勧請した時点で、彼らはすでに大内の住人であり、氏寺も建立するほど根を張っていたのである。
しかし、この時点で、氏寺・氏神一所の繁栄がどの程度だったのかは、残念ながらわからないというほかない。最近は、歴史学も「史料」「史料」の一点張りではなく、考古学の分野とタッグを組んで発掘調査などにも熱心であるようだ。やがて技術が進めば、往時の興隆寺の繁栄ぶりも CG 化される日が来るかも知れない。その頃には、氏寺・氏神一所になったのが、茂村代だったのか、だとしたらそれはいつ頃のことなのか、その当時の氏寺・氏神の規模はどのくらいだったのか、などが、次々と明らかになるかも。今はただ、その日が一日も早く来ることを望むだけ。
ちなみに『大内氏史研究』はたまに脱線しているが、愛ある脱線はむしろ麗しい。郷土史研究家と歴史学者の微妙な温度差かもしれない。最近、尊敬する軍事評論家の先生(今は歴史研究家になられた)が、「軍記物」は史料扱いされないことが多いけれどもとういうようなことを書かれていて、貴重な一次史料とされている「貴族の日記」にも単なる噂話をメモっただけの部分があり云々と書かれていた。まだ、立ち読み段階なので、引用できずもどかしい。寺社日記なんて、「今日となりの寺の坊さんが来て、〇〇家の騒動について噂していった」とか書いてあることが。こういう噂話が混在したものを鵜呑みにするって、どこが「超一級史料」なんだろう? 落雷必至だけど、郷土の伝承を拾っていく作業と、学術論文はそもそも次元が違う。ゆえに、怒られる筋合いはないはずだ。
茂村期のほかの出来事(『伝』)
例によって例のごとく、『大内文化研究要覧』を確認しておくと、茂村が妙見社を勧請した前後の文化的な出来事が年表になっている。そもそも茂村の治世がいつからいつまでなのかすら不明であるから、どこから引用すべきか悩ましいが、ほかの当主は何一つ事蹟がわからず項目を立てられないから、800年代と900年代のことをすべて載せる。すると、何とも恐ろしいことが分かる(後述)。
- 大同元年(806) 清水寺(山口市宮野)が建立される。平城天皇の勅願寺、天台宗、「山口地方最古の寺院」
- 大同四年(809) 宇佐から、平清水八幡宮を勧請(誰が?)
- 天長四年(827) 下松妙見社勧請
- 貞観元年(859) 宇佐から、朝倉八幡宮を勧請(誰が?)
- 承平元年(931) 茂村、桜木神社(大内矢田)を創建
さて、まずはものすごい矛盾が二つある。気付いた方はおられるでしょうか。
一、「山口地方最古の寺院」が清水寺であるならば当然、興隆寺はそれよりも後に建立されたことになる。始祖創建の年代「613」(前述)が誤りなのか、清水寺のほうが間違っているのか、もしくは興隆寺の所在地は「山口地方」ではないのか、ということになる。もしかしたら、「山口地方」ではないのかも知れない(この時代どこからどこまでが『山口地方』だったのかなど、この記述からは分からない)が、現代の感覚だと当然、山口市内にあるところはすべて山口地方だと考えてしまうので、両寺院とも同地方にある、と考える。どちらが誤っているかと考えた時、疑わしいのは当然、興隆寺のほうだろう。創立者が実在したかどうか不明な人物であるのだからして。
二、妙見社の勧請は「827」。茂村によって行なわれた。そして、その後、茂村は桜木神社も創建している。その年代は「931」。二つの年代間には、なんと、104年の開きがある。普通に考えてこれは不可能。やはりどちらかが間違っていることになる。
大切なことは、これらの年代がすべて「伝承」の二文字を冠していること。つまり、「言い伝え」扱いにされる寺社の縁起や由緒が典拠となっている点。確かにわずかにこれだけの事柄にも矛盾があり、研究者が正式な史料として認めたがらないのも分かる気がする。もちろん、由緒ある寺社の縁起や由緒がすべてデタラメだなどと言っておられる先生方はおられず、いずれも貴重なものであることは間違いない。中にはその信憑性が高く評価されているものも少なくない。ただ、時代が古くなればなるほど、信憑性は薄れていくような気がする。そもそも、記録じたい極めて少なく、時代の全貌すらわからない。ここらはもう、正確さを求めるのは無理なのだろう。
では、大内氏の氏寺・氏神の正確な起源は分からず終いなのか? 残念ながら、限りなくそうであると言うよりほかないようで。ただそれは、実は、ほかのどの一族についても同じなのではないか、そう思う。
まとめ
多々良茂村の事蹟
わずかに一行。「妙見社を氷上山に勧請した」。
ほかにも、桜木神社を創建したという言い伝えがあるが、年代的に合わない。時代が古すぎるゆえに、茂村が創建したことは正しく、年代その他の記録が誤っている可能性は残されている。
茂村の子孫
「新撰大内氏系図」によると、茂村の後の当主は以下のように繋がっている。
茂村ー保盛ー弘貞ー貞長ー貞成ー盛房……
最後の十六代・盛房が、「史料に現われる最初の人」であるから、彼を境に様々な記録がどっと出てくる。それまではやはり、「暗黒時代」が続く。
お気づきの方もおられたと思うが、「伝」始祖来朝とされる推古天皇の飛鳥時代から、茂村の妙見社勧請時にはすでに平安時代(794~)へと時が移っている。史料に現われる盛房代は長く続いた平安時代も末期の頃となっており、結局のところ、それまでの長い長い時間、大内氏の先祖たちについてはほぼ謎である。
記録に残されてはおらずとも、祭祀は史料に乏しい古代史の時代から、文字史料が現われるようになる時代まで欠かさず続けられてきた。氏寺も、妙見社も、たとえその姿が大きく変ろうとも、現代に至るまで目に見える形で残されている。先祖たちが実在したこと、彼らの手で氏寺、氏神が守られてきたことは紛れもない事実(史実)である。たとえ史料がなくとも、研究者の先生方もそのことは否定なさらないだろう。実在した当主の名前や身分などには、多少事実とは異なる部分もあるかもしれないし、神がかった出来事は単なる言い伝えの可能性もある。年代も不正確かも知れない。
しかし、先祖なくして現在の我々はいない。大内氏は残念ながら滅亡したから、直系の子孫はいない。でも、かつて華やかなりし頃、活躍した彼らに先祖が存在しないはずはない。たとえ、異国の王子ではなかったとしても。なお、嫡流は途絶えても、分家の方々がその後も繁栄を続けたことはよく知られている。県の内外を問わず、名門一族の末裔を名乗る方々は大勢おられる。
参照文献:『大内文化研究要覧』、『大内氏史研究』、『新撰大内氏系図』、『大内村誌』
やっぱり、大内氏のルーツは下松なんだね。氏寺まであったかもって『大内村誌』が書いちゃうところがすごいよね。
そうだね。でも、長らく大内文化の中心地だって誇りがあるから、最初は下松だったとしてもいいよって、寛容なのかな?(結局の所、古い話は誰にもわからない。本人たちが茂村代に山口へ勧請したと自白している以上、最初は山口には氏神社はなかった。だったらもう、琳聖が上陸したのも下松、ルーツもそっちって仮説もありじゃないのか、そんくらい分かんないだって話。この辺、ちょっとややこしいので、すこし時間をください)。
ふふん。でも、ルーツってすごい貴重だよ。俺、周南より陶がルーツって思うもん。ミルって東国がルーツの荒くれ者の子孫だから、隠し通すのがたいへんだね。
(はっ!)いえ、ルーツは南海道です。つーか、大内氏のルーツは大内ってことで……。
(苦しい言い訳)。ひょっとして、茂村って人が大内に引っ越したのかな? 氏神さまをお連れして。古すぎてなにもわからないね……。
【更新履歴】20250815 テーマ変更によるレイアウト調整、加筆修正、リンク追加