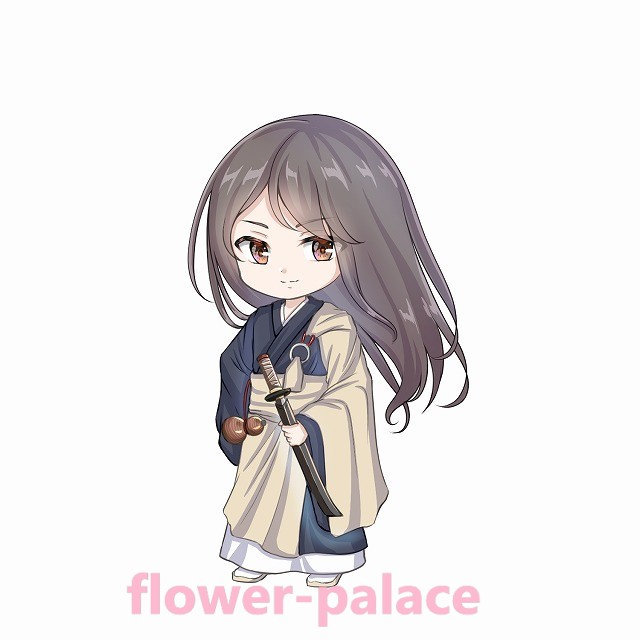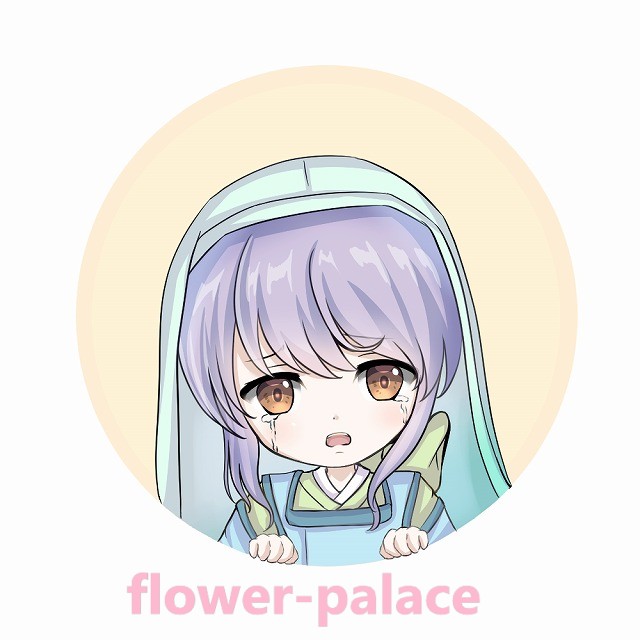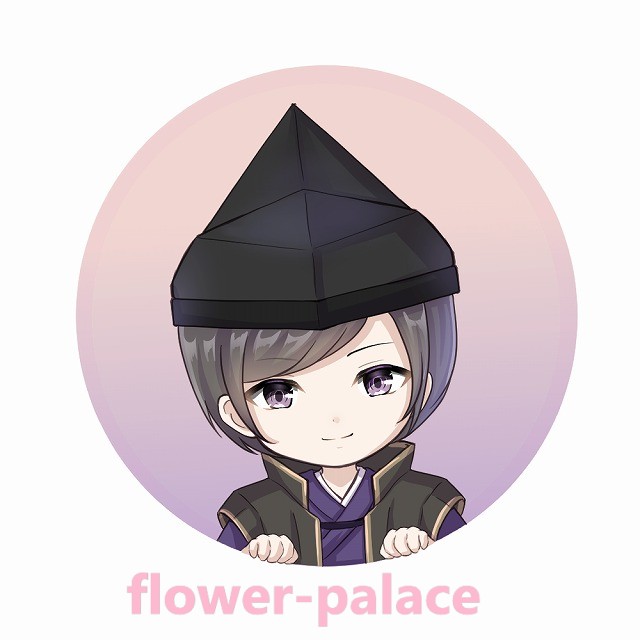史跡巡りガイド– category –
-

厳島大明神信仰とは? 市杵島姫命と弁財天
厳島大明神とは厳島神社のことを指す。「大明神」が神さまの尊称なので、その意味では無数の〇〇大明神が存在する。神仏習合の時代、厳島神社の祭神・市杵島姫命と弁才天は習合していた。ゆえに、弁天参りが盛んになると同時に厳島信仰も大盛況となる。 -

寺院建築の基本① 伽藍と伽藍配置
寺社巡りガイドブックの寺院建物編。伽藍というのはつまり寺院の建物。古代は○○式などと呼ばれる建物配置(伽藍配置)の雛形みたいなものがあって、受験勉強で暗記させられる。その後も建築様式や伽藍配置は時代によって変化。ものすごく簡単に眺めてみた。 -

山王権現とは? 中世延暦寺と日吉神社
この記事を見てわかること 山王権現とは何か? 日吉神社と延暦寺の関係は? 「山王七社」って何?(中世編) そのほか中世日吉神社と天台宗のあれこれ 大内氏の活躍した... -

八坂神社の前身・祇園社と牛頭天王
牛頭天王とは? 「ごずてんのう」と読み、祇園社(現・八坂神社)、津島社(現・津島神社)などにお祀りされていた神様。インド・祇園精舎の守護神で、神仏習合の時代、素戔... -

熊野権現とは(中世の様相)
熊野権現とは? 熊野の本宮、新宮(速玉宮)、那智の三山を総称したものを 「熊野三所権現」呼んでいました。現在、熊野古道と参詣道として、世界遺産にも登録されており... -

八幡宮 & 八幡信仰とは?
八幡さまとは何か? ということで、八幡宮のご祭神、総本宮・宇佐八幡、源氏の氏神・石清水八幡宮、神仏習合した「八幡大菩薩」なんかの話をしています。宇佐八幡宮は大内氏の分国豊前国にあったことからその関わりについても触れます。 -

妙見菩薩、妙見信仰とは?(超簡単に)
大内氏の氏神として有名な「妙見菩薩」。遊牧民の北極星・北斗七星信仰が、中国で道教と習合。のちに日本に輸入された。密教と強く結びつき、日本独自の「妙見信仰」となる。のちには、武士階級も「軍神」として崇拝した(千葉氏、秩父氏、相馬氏等)。 -

神社の格式【超・基礎編】
神社の格式の話。昔々に書かれた「延喜式」の中に全国神社名簿みたいなものが。そこに名前が載っているか否かで、神社の「格」はぐーーんと変わるよ。 -

神社のお名前 名は格を表わす【基本編】
○○神社、○○社、○○宮……と、神社さまのお名前も色々。じつは、古来、神社には格式があって、厳格なランク付けがあったんです。まあ、最初はお名前についてだけ。 -

神社の構造基本編 & 楼拝殿造りについて
神社の基本構造と、山口県独特の建築様式とされる「楼拝殿造」についてのきわめて基本的な説明。
12